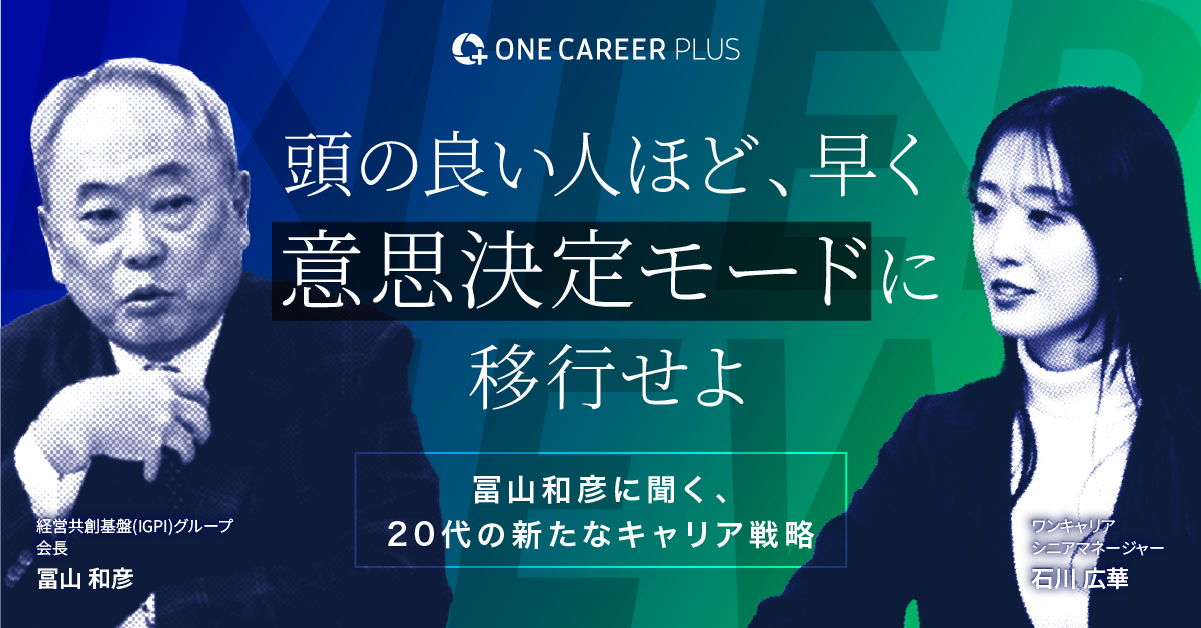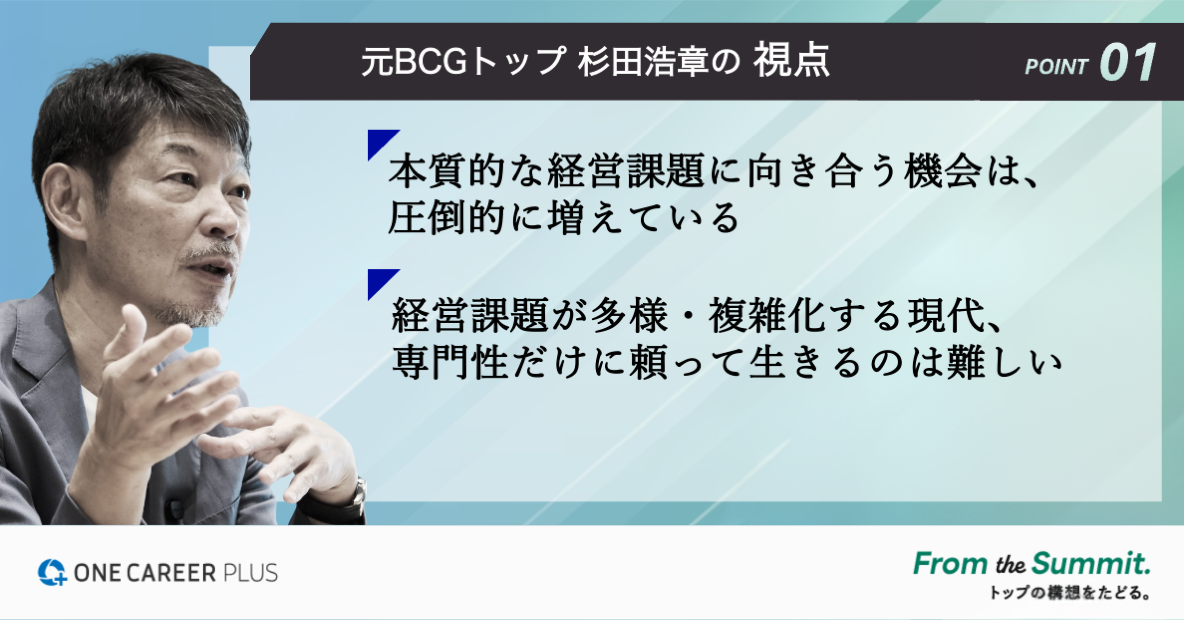「コンサルは潰しがきくキャリア」という定説が揺らぎつつある。コンサルで身に付くスキルの一部はAIで代替可能となり、IGPIグループの冨山和彦会長からは「パートナー未満は潜在的リストラ対象」との発言も飛び出した。
では、激変する時代において、真に「替えがきかない人材」となるためには、私たちはどのようなキャリアを目指すべきなのだろうか。
その答えの一つとして「プロフェッショナル経営参謀」を提唱するのが、ボストン コンサルティング グループ(BCG)の元日本代表の杉田浩章氏だ。
30年以上にわたり経営コンサルティングの最前線で数々の企業変革をリードし、スタートアップのアドバイザーも務める杉田氏は、社会にインパクトを生み出す上で3つの本質的な力の重要性を説く。
マッキンゼーを経て、現在ワンキャリアで事業開発を務める石川がファームトップの思考に迫る特集『From the Summit ─ トップの構想をたどる』。今回は杉田氏に代替不可能なプロフェッショナルになるためのキャリアの歩み方を聞いた。
杉田 浩章
ボストン コンサルティング グループ シニアアドバイザー/早稲田大学ビジネススクール教授
東京工業大学工学部卒。慶應義塾大学経営学修士(MBA)。株式会社日本交通公社(JTB)を経て1994年にBCG入社。2006〜2013年BCG日本支社長、2016年〜2020年同日本代表、2023年より同シニアアドバイザー。2021年より早稲田大学ビジネススクール教授。BCGでは様々な企業の再成長に向けたトランスフォーメーション、事業ポートフォリオの変革、新規事業開発、組織・ガバナンス改革、マーケティング・営業戦略などのコンサルティングを数多く手掛けた。現在は複数の大企業、スタートアップ、VCなどの社外取締役、顧問を務める。主な著書に『スタートアップの技法 新規ビジネスをスケールさせる「7つの視点」』『プロフェッショナル経営参謀』『10年変革シナリオ』(いずれも日本経済新聞出版)など。
石川 広華
ワンキャリア ONE CAREER PLUS事業部 シニアマネージャー
新潟県出身。京都大学法学部卒業。新卒でマッキンゼー・アンド・カンパニーにコンサルタントとして入社。小売・製造・エネルギー・官公庁・金融・通信など多岐にわたるプロジェクトに従事し、プロジェクト外の組織活動のリード経験も多数。現在は、株式会社ワンキャリアの中途事業 ONE CAREER PLUSにて、事業開発 / シニアマネージャーとしてコンテンツ・メディア領域をリード。
インパクトなきコンサルは意味がない
石川:杉田さんは、BCGの元日本代表というご経歴を持ちながら、現在はアカデミアやスタートアップ支援など、多岐にわたる活動をされています。そのような時間の使い方をするシニアアドバイザーは珍しいと思うのですが、根底にはどのようなライフミッションがあるのでしょうか。
杉田:私が他のコンサルタントよりもずっと意識してきたことは、結果として何かが具体的に変わること、目に見えるインパクトが生まれることを、昔から何よりも重視してきた点です。コンサルタント人生における矜持とも言えますね。
「コンサルタントは第三者であることが最大の価値だ」という意見もありますが、私はBCGに入社した頃から「そう思わない」と言っていました。自分がこの会社を変えていくんだというマインドやコミットメントでインパクトを出すべきだと考えていました。第三者の役割で終わるのは嫌だという考えをずっと貫いてきました。
石川:経営トップの意思決定に関与し、当事者意識を持って企業を動かしていく。まさに経営参謀の役割を果たしてこられたのですね。
杉田:どれだけ美しい戦略を描いても、現実に何も変化が起きなければ意味がないと考えています。
どのような仕事をするにしても「最終的にインパクトに繋がるのかどうか」という一点を常に問い続け、そこに繋がらなければ「やっている意味がない」とまで考えて仕事に取り組んできました。
逆の言い方をすると、いくらお金を払ってくれようとも、変化が起きない企業には自分の時間を使いたくありません。だから、本当に変えていく気があり、変えられるだけのポテンシャルがある企業や組織とだけ付き合ってきました。
石川:関わり方は違うにせよ、全ての活動は「カウンターパートと共に、具体的な変化を起こせるかどうか」にかかっているのですね。
「専門性」が武器のコンサルは淘汰される
石川:杉田さんのように社会にインパクトを与える人材になりたいと、コンサルを目指す若手もいます。
一方で、業界としては採用人数が増えて産業化が進み、実態として若手は「定義された問い」だけを効率的に解く仕事を行っている印象も受けます。経営参謀として働ける機会は、今のコンサル業界にあるのでしょうか。
杉田:企業全体を変えていくような本質的な経営課題に向き合える機会は、昔と比べて圧倒的に増えています。
私がBCGに入った1994年当時、コンサルは企業の積年の課題解決や中期経営計画の策定といったオケージョナル(一時的)な関わり方が主流でした。それが2000年頃から年間契約を結んで、企業と伴走しながら変革に取り組む形になりました。
その流れは加速しており、今ではスピード感を持って企業のポートフォリオを変えていく、組織のケイパビリティを革新していくといった支援が主流になりました。かつては一つの企業において10年に一度くらい大きな問いに向き合えばよかったのが、今はそうした営みを常に続けなければならない時代です。
石川:変化が激しい分、解くべき経営課題自体はむしろ増えている、と。
杉田:そうです。ただ、経営課題に向き合う機会をつかめるかは、個人差があります。目の前の業務について「全体の流れの中で、どのような意味を持つのか」と常に自分の仕事の価値を考えるのか。もしくは、自分のスキル・時間への対価を得るものと捉え、なるべく効率的に生産性高くやろうとするのか。
これは個人のスタンスの違いですが、後者のように自分が持っている専門性を提供することをコンサルティングと定義すると、その人たちは生きにくい世の中になっていくでしょう。
石川:どういうことでしょうか?
杉田:例えば、AIを活用するプロジェクトで、専門性が高い人材がクライアントにはない知見を提供し、支援をするケース。コンサルティングとも言えるかもしれませんが、その人の専門性で企業に足りないピースを補うという点で、本質的にはアウトソースに近いです。
今は高度な専門性を持っていたとしても、時代と共に劣化していきますし、AIやテクノロジーが進化したら置き換わってしまいます。事業環境が目まぐるしく変化し、解くべき経営課題も多様化・複雑化する中で、今ある専門性だけに頼って生きていくのは難しいでしょう。
替えがきかない「プロフェッショナル経営参謀」の3つの力
石川:では、スポット的なアウトソースではない「本質的なコンサルティングの力」とは、どのようなものでしょうか?
さらに・・・