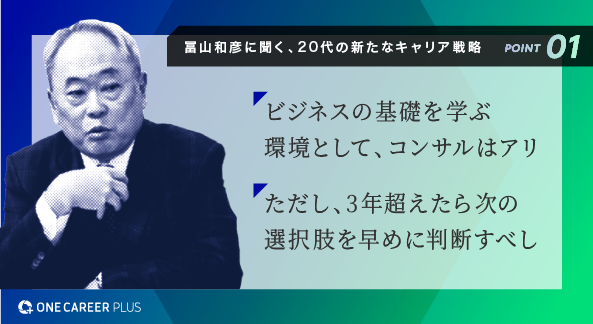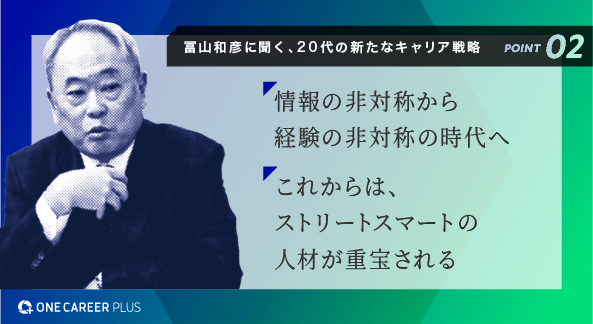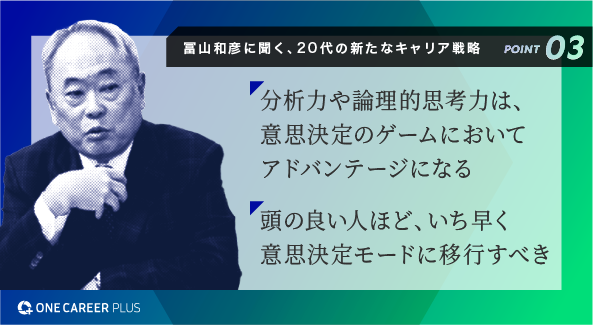パートナー未満のコンサルは潜在的リストラ対象ー。
そう語るのは、IGPIグループで会長を務める冨山和彦氏。冨山氏はBCG、CDIの代表取締役を経て、産業再生機構のCOOに就任。これまでJALやダイエーといった大手企業から地域のローカル企業まで、数多くの企業の再生や経営改革に携わってきた経営のプロだ。
就職・転職市場問わず人気の業界である「コンサル」に今、何が起きているのか。市場価値を高めたい若手社会人は、今後どのようにキャリアを築いていけばいいのか。
マッキンゼーを経て、現在ワンキャリアで事業開発を務める石川が、悩める若手社会人を代表して冨山氏に疑問をぶつける。
冨山 和彦
IGPIグループ 会長/ 日本共創プラットフォーム(JPiX) 代表取締役会長
ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、2003年 産業再生機構設立時に参画しCOOに就任。解散後、2007年 経営共創基盤(IGPI)を設立し代表取締役CEO就任。2020年10月よりIGPIグループ会長。2020年 日本共創プラットフォーム(JPiX)を設立。パナソニックホールディングス社外取締役、メルカリ社外取締役、日本取締役協会会長、政府関連委員多数。東京大学法学部卒、スタンフォード大学経営学修士(MBA)、司法試験合格。
石川 広華
ワンキャリア / ONE CAREER PLUS事業部 シニアマネージャー
新潟県出身。京都大学法学部卒業。新卒でマッキンゼー・アンド・カンパニーにコンサルタントとして入社。小売・製造・エネルギー・官公庁・金融・通信など多岐にわたるプロジェクトに従事し、プロジェクト外の組織活動のリード経験も多数。現在は、株式会社ワンキャリアの中途事業 ONE CAREER PLUSにて、事業開発 / シニアマネージャーとしてコンテンツ・メディア領域をリード。
生成AIの時代、パートナー未満は潜在的リストラ対象
石川:「市場価値をあげるならここへ行け」という、キャリアの人気トレンドは、銀行、コンサルと変遷してきました。
就職市場でも転職市場でもコンサル業界が大人気である一方、「とりあえずコンサル」が今後通用しなくなることに気づく人も増えています。
冨山:今のコンサルの仕事は、昔と比べてかなりシステマティックになっているんですよ。
しかも、20代や30代前半の若手に経営の根幹に関わる意思決定の仕事は回ってきません。パートナーまでは、意思決定のための材料を集めるとか、その前提となる分析をするとか、インプリメンテーションサポートの仕事が中心になる。
ただ、それらの仕事はAIに代替される可能性が非常に高い。最近はOpenAIの「ディープリサーチ」が話題になりましたが、ディープリサーチがあればプロジェクトマネジメント未満の仕事は不要です。
AIの進化のスピードは目覚ましいため、パートナー未満は潜在的なリストラ対象と考えておいた方が良いでしょう。
石川:コンサル組織のほとんどがAIに代替される可能性があるということですね…。
3年で成長曲線は鈍化する。コンサルキャリアを見直す時
石川:逆に、今若手にとってコンサルに入るキャリアの旨味はあるのでしょうか。
冨山:ビジネスの基本設計を学ぶ場所としては良いと思いますよ。例えば、PL/BS/CFなどの財務諸表を読み解く力や、事業経済性や簿記会計に関する知識などは、どこに行っても役に立ちます。リサーチや資料作成がAIに代替されたとしても、AIのアウトプットを正しく読み解く力は必要ですから。
石川:確かに私自身、新卒でマッキンゼーに入社して3年働きましたが、ビジネスのベースとなるハードスキルを身につけられたのは良かったと感じています。
冨山:3年は、ちょうどいいタイミングですね。3年を超えると成長曲線が鈍化する人が多いんですよ。
石川:どういうことでしょう?
冨山:多くの人はコンサルに入って2-3年で、ビジネス基礎を身につけることができます。しかし3年を超えて慣れてくると、型通りにやっていればこなせてしまう仕事も増えてくるんです。
その次のステージとして、コンサルとしてのキャリアを突きつめてマネージャーやパートナーを目指すこともできますが、上にいけばいく程セールススキルが問われるフェーズになります。
セールススキルはインターパーソナルな要素にも大きく左右されるため、コンサルでしか経験がない人は苦戦することも多いのです。
石川:確かに、パートナーとして活躍される方はコンサルに中途入社しているケースも多い印象です。
冨山:こうしたことを踏まえ、30代前半ごろまでには「コンサルタントとしての道を極めるのか、事業経営にいくのか、あるいは実事業や実投資にいくのか」を早めに判断した方がいいでしょう。
ニッチから巨大産業へ。裏で加速する、コンサルスキルの一般化
石川:経営の近道になると考えて、コンサルを選択する人は多くいます。コンサル出身の経営者は冨山さんに限らず多くいらっしゃいます。
ただ、今のお話を聞くとコンサルを選ぶことが必ずしも経営人材に近づくわけではない印象を受けました。コンサルで得られる経験が変化しているのはなぜでしょう。
冨山:私がいた1980年代当時のコンサル業界というのは、今よりずっと乱暴だったんですよ。当時20代前半の私が、いきなり1人で社長にプレゼンをしにいく、なんてことが当たり前にあった。
その後、コンサル業界が拡大するにつれて多くの組織で機能化が進みました。どんなビジネスでも拡大の過程では、再現性・効率性を高めることが求められます。いま、平均的な優等生がコンサルで飯を食えるということはコンサルが産業化したということなんです。
石川:確かに、人月でフィーが決まるコンサルのビジネス構造や人が原材料になることを考えると、仕入れと売りの効率を高める観点でコンサルタント一人ひとりの仕事が効率化されていくのは自然な流れですね。
冨山:産業化の裏を返せば、その人固有の価値が問われなくなるということ。個人のキャリアの観点でいえば固有名詞で勝負できる方が代替可能性が低いことはいうまでもありません。
加えて、昔はコーポレートファイナンスやバリュエーションの基礎知識は、MBAに留学しないと学べなかったんですよ。情報の非対称があったから、MBAを持っていれば投資銀行に転職できるなどキャリアの選択肢がたくさんあった。ただ、今はそうした知識もコモディティ化しています。
若手の新たなキャリア戦略「経験の非対称で勝負」
石川:情報社会において、昔はコンサルの専売特許だった知識が体系化されたことで情報の非対称が解消されてきたということですね。
「たくさん勉強して、多くを知っている」ことだけでキャリアの差別化を図るのが難しい時代だとすると、コンサルに長くいつづけることで市場価値が高まるわけではないと納得できます。
これからは、どのようなことを意識してキャリア戦略を考えれば良いのでしょう。
冨山:情報の非対称が解消されれば、次は経験の非対称で勝負する時代がきます。 「ブックスマート」「ストリートスマート」という言葉がありますが、キャリアトレンドとしてストリートスマートの人材が重宝されていくのは間違いないでしょう。
そのため、ビジネスの基本知識をある程度身につけた後は、いち早く意思決定モードに移行できるかどうかが重要です。
石川:意思決定、ですか。
冨山:コンサルは自分で意思決定をしないじゃないですか。同じことをやっているように見えても、意思決定した結果が全て自らに返ってくるという点で、サポートする立場と意思決定する立場は全く違います。
経営人材を目指すならもちろんのこと、AIに淘汰されない人材を目指すにしても「意思決定力」を身につけることは重要です。AIが意思決定の結果に責任を持つことは難しいですから。
石川:たしかに、経験の非対称で勝負するのであれば、より早い段階で経験を積み上げられるよう行動した方が良さそうです。
優等生は分析しすぎ?失敗してから本当の学習が始まる
冨山:注意してほしいのは、優秀なコンサルタントタイプの人ほど、いざ自分でものを決める立場になると、意思決定力が低い傾向にあるということです。
石川:それはどういうことでしょう。
冨山:分析しすぎなんです。そもそも、意思決定の精度には限界効用の逓減の法則が働いていて、分析量に比例して精度が上がるというものではありません。
どれだけ分析しても、すべての可能性は排除できないし、途中で状況の変化もおこるので、不確実要素は残る。
どこかのタイミングで腹決めして選択する必要があるのですが、優等生タイプほど正解を出そうとロジックを詰めすぎて意思決定を先送りにしてしまいやすいんです。私が何で決めてるかと言えば、ほとんど経験則と直観です。
石川:経験則と直感ー。そうすると、若手で意思決定する人は失敗だらけになりませんか?
冨山:失敗しますよ。意思決定なんて、9勝6敗だったらすごく優秀な経営者です。自分で決めると手痛い失敗が必ずあります。ただ本当の学習が始まるのは失敗してからなんです。
だからこそ、若いうちから意思決定をする立場になって、経験則と直感を作る必要があるんです。
頭の良い人ほど、いち早く意思決定モードに移行せよ
石川:私自身もそうですが、読者の中には学生時代に勉強を頑張って、良い大学に入り、就職活動でも良い結果を残してきたという「優等生タイプ」の人が多くいます。
分析しすぎが良くないことは分かります。とはいえ、これまで培ってきたものと全く違う土俵で戦わなければいけないような気がして、喪失感や不安を感じる人も多そうです。
冨山:正解のある問いをいち早く解くことが求められる日本の教育システムで優等生だった人ほど、そう思うのも無理はないでしょう。私も東大法学部、司法試験合格、と超優等生の道を歩み続けてきました。
ただ、お伝えしたいのは勉強ができるということ自体はむしろアドバンテージですよ。意思決定をするうえで、イロジカルな選択肢を排除するための分析は必要ですから。
頭の良い人は数ある選択肢の中から良くないものを排除して、いち早く可能性を3つぐらいに絞ることが得意です。
石川:なるほど。
冨山:分析やロジックが得意な人であれば、そのベースを活かして次のゲームに移ればいいだけなんですよ。
石川:ここまで身に着けてきた知識や思考力があるからこそ、ロジカルさが重視されるような自身の得意な領域に固執せずに、意思決定の領域にキャリアを拡張しないとむしろもったいない、ということですね。
石川:今は、転職市場においても学歴や社名ではなく実務経験の豊富さがシビアにみられるようになっています。
冨山:私はどれくらい事業をやってきたかを見ていますよ。話していればわかりますが、眉目秀麗なロジックを語る人は大体自分で決めていない。意思決定は論理的に美しくないものなので。
また、昔の日本企業は失敗に寛容でない風潮がありましたが、今はアメリカと同じように失敗経験をむしろ評価する経営陣も増えてきました。世の中の見方もかなり変わっているので、失敗することを過度に恐れなくていいんですよ。
「意思決定の経験を磨けるキャリア」企業選びのポイント
石川:では、具体的にどのような場所であれば、意思決定経験を磨くことができるのでしょうか。
冨山:若い人であれば、スモールビジネスがおすすめです。スタートアップや中小企業など、意思決定もその後のエグゼキューションも全て自分でやる環境であれば、自身の意思決定の愚かさがいやというほどわかります。
石川:読者の中には大企業で規模の大きい事業・経営の意思決定に関わりたいと考える人も多いと思います。そうした選択肢はいかがでしょう。
冨山:30歳ぐらいの若手が大企業の経営の意思決定を行うのは危険です。現場のリアルがわからないのですから。
例えば人事評価制度を変える意思決定一つにしても、その変更で現場がどんな反応をするか想像がつかない。頭で考えて「経済的インセンティブでこうなるだろう」と予測をしても現場では、経済的インセンティブが全く効かないなんてことが起こり得るんですよ。
これまで意思決定をやってこなかった人が、突然大企業の経営の意思決定に入っても現場から総スカンを食らってしまいます。
石川:意思決定の経験を積むという意味では、あくまで現場を知り得える規模の組織で自らの意思決定の責任を持つ方がいいということですね。
冨山:そうです、40〜50人ぐらいまでの規模が良いですよ。
スモールという意味ではスタートアップも良いのですが、気をつけて欲しいのはエリートだらけの人員構成の場合です。世の中の働き手のマジョリティをマネージできる力がなければ、本当の経営者にはなれません。
若手を飛躍的に成長させる「VENTURE FOR JAPAN」のプログラム
石川:冨山さんがボードメンバーを務める一般社団法人VENTURE FOR JAPAN(以下、VFJ)では、まさしく20代の若手が地方の中小企業の経営陣として意思決定を行う機会を提供しているそうですね。
【VENTURE FOR JAPANとは】
新卒・20代の若者が、ローカルの先進企業に、経営者直下の事業責任者として就職・転職する2年間のプログラム。VENTURE FOR JAPANに参加した若者は、研修・メンタリング等のサポートを受けながら、経営者の右腕として働き、2年間で経営力を身に着けることを目指す。これまで累計50名以上の若者が、全国各地で企業、地域、社会の課題解決に挑戦してきた。2年の就業後のキャリアは若者自身が選択し、プログラムのOBは、起業、企業の中核人材として就業継続、経営に関わるポジションへの転職など、各方面で活躍している。
VFJのプログラムに参加すると、具体的にどのような経験・スキルを身につけることができるのでしょうか。
冨山:新卒・第二新卒の若手がいきなり、経営の意思決定に関わることは難しいので、最初はブートキャンプとしてビジネスの基礎を徹底的に学んでもらいます。事業経済性や財務モデリングなど、コンサルで学ぶような知識もここで身につけます。
その後は、各企業で経営者直下の事業責任者として2年間働きます。事業立ち上げや撤退、時にはリストラなども当事者として意思決定を行う立場であり、タフアサインメントではありますが生きた経営力が身につきます。
プログラムが終了する2年後には、就業継続もできるし、転職も可能です。起業、大手企業の経営に関わるポジションへの転職など多方面で活躍していますよ。
もともと米国にVenture for Americaというフェローシップがあり、非常にスマートで起業家・経営者志望の若手人材が自らの経験を積む場となっており、日本にも絶対必要と思い支援しています。
私の経験上はっきり言えることは、若手のうちからこうした痺れるような経営や事業の最終意思決定にかかわることが、その人を飛躍的に成長させます。
優等生的ではない意思決定・失敗を30歳までに取りに行けるか?
石川:最後に、市場価値を高めたい・経営人材を目指したいと考えている読者にアドバイスをお願いします。
冨山:まず知っておいてほしいのは、経験の非対称の力は強烈ということです。
私は今も、著名企業の経営の意思決定に関わることが多いのですが、戦略コンサルに頼むと数億円の金額がかかる意思決定が、私を使えば1回の会食で済むんですよ。
これが実現できるのは、AIで知識のリニューアルが簡単にできることと、私の経営に関する経験量が圧倒的でトップ経営者と対峙した時にデジャヴ感で答えがわかるからです。
そして繰り返すようですが、いま私が正しい答えが導き出せるのは、私の学生時代の頭の良さによるものではなく、30歳ぐらいから積み上げてきた現場での意思決定や失敗の積み重ねがあったからなんですよ。いきなりこんな風にはなれませんでした。
石川:冨山さんの事例は経験の非対称で勝つキャリアの最たる例なんですね。
冨山:そうですね。若手社会人の皆さんへのアドバイスは、できれば30歳まで、遅くとも35歳までに「自ら意思決定をしてその結果を自ら受け止める」という経験を積めるキャリアに転換しましょうということです。
幸いなことに、世の中では変化が起きていて、若手のうちから経営の意思決定に関わるチャンスは広がっています。
特にVFJのような中堅・中小企業の若手受け入れ需要は皆さんが思っているより上がっていて、需要があって行く人が少ないのでチャンスと言えます。 ムーブメントが起こる前に動いた人がより有利です。
石川:冨山さんは黎明期のコンサルに身を置き、今経営者として活躍していますが、それと同じようなことが、これからはスモールビジネスの領域で起こるということですね。
冨山:コンサルで経験を積んだ人であれば情報の非対称・経験の非対称の掛け算で勝負できれば、稀有な人材になっていけるはずです。是非、そうしたキャリアに挑戦してください。