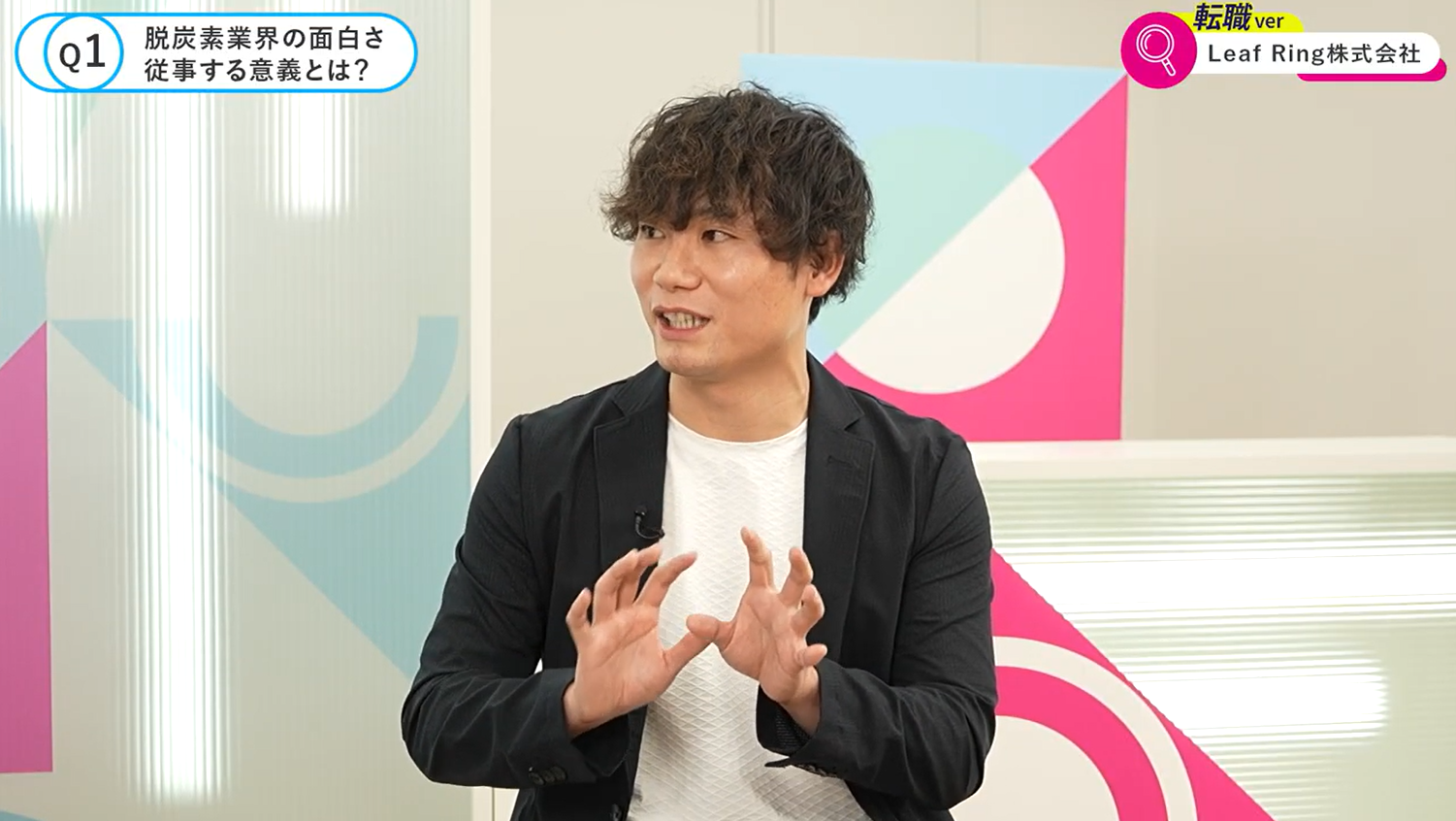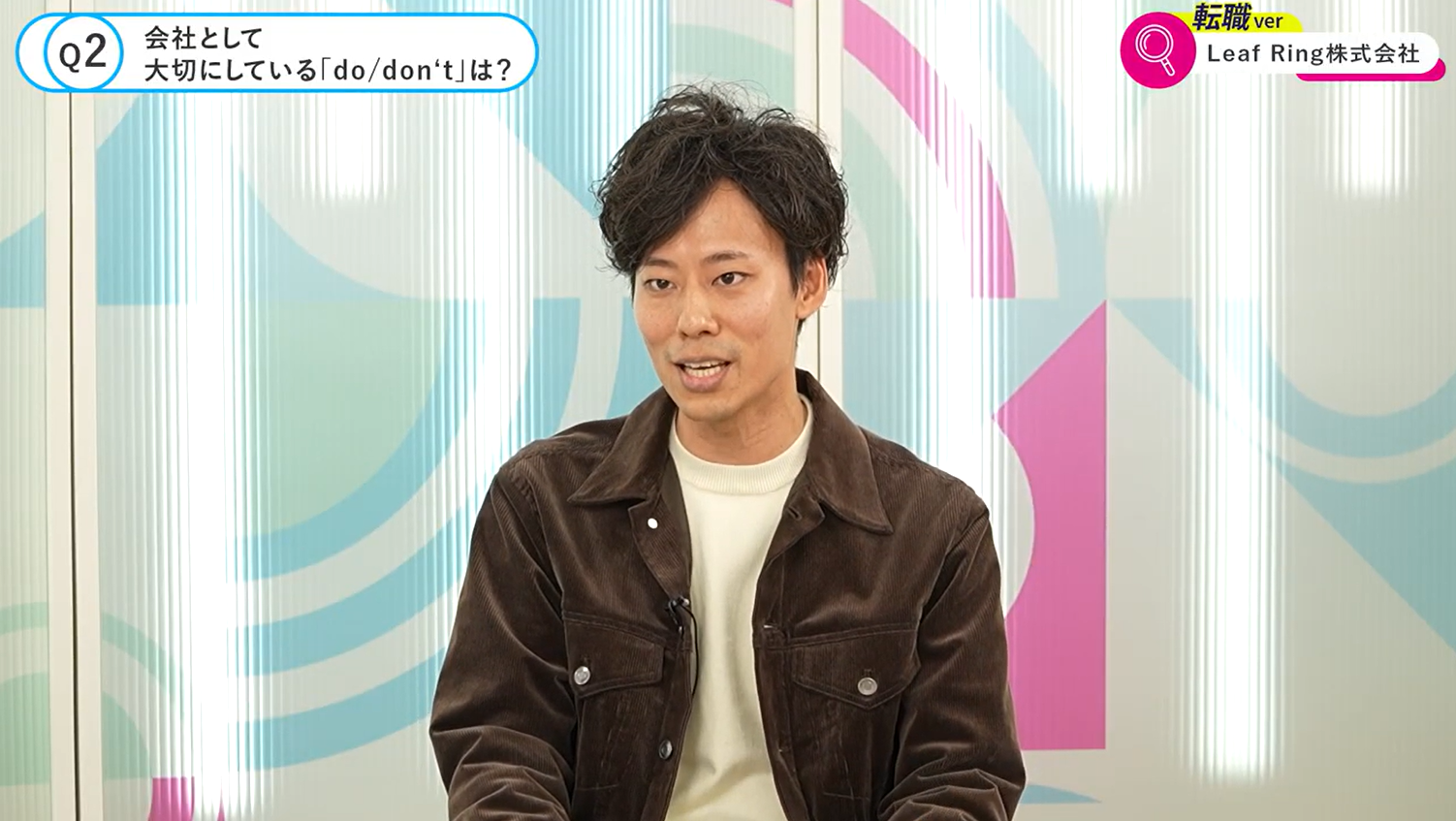ワンキャリアプラスがお届けする転職向け「ワンキャリアプラス企業説明会」。
様々な角度から企業の魅力を掘り下げる動画内容の一部を、こちらの記事でもお届けします。
今回出演いただく企業様は「Leaf Ring株式会社」です。
Q1. 脱炭素業界の面白さ、従事する意義とは?
──近年、盛り上がっている脱炭素業界ですが、魅力は何でしょうか?
及川:脱炭素業界はかなり未成熟なので、企業の担当者でも採用要件が見えていなかったり、補助金などの制度が激しく変化するのを日々感じたりするところが面白味でもあり、難しいところでもあります。また、業界のキャッチアップをしたり、企業の担当者と一緒に採用要件を決めたりすることで、脱炭素に専門特化したエージェントとしての介在価値が非常に大きいと感じています。
──具体的な事例を教えていただけますか?
及川:物流系の貿易輸送などを経験され、再エネの領域は未経験という候補者を約1年支援したことがありました。一般的に50歳前後の年齢は難しく、再エネの領域ではまだ輸送のポジションが少ないため、なかなか決定に至りませんでした。最初、企業の反応は厳しかったのですが、希少性がある経験の周辺領域という観点を伝えることで面談していただくことができ、決定に至りました。
これは、採用要件がなかなか見えない中でも、弊社が「この方なら」ということを専門的にやっているからこそ決定に至った事例だと思います。
──総合型エージェントでは難しくても、専門性があり、クライアントに入り込んでいる御社だからこそご支援できるのですね。
及川:企業様とのミーティングでも、かなり深く入り込んで事業の現状などを聞き、候補者に伝えることで、マッチングの精度が上がっていると思います。
──今後の中長期的な事業や、業界の展望を教えていただけますか?
及川:「脱炭素」は社会課題であり、汎用性が高いです。弊社では「脱炭素×教育」「脱炭素×コンサルティング」など、人材から派生する注力領域が考えられます。その他にも地域創生や不動産など、事業を立ち上げる領域はかなり広いと思います。
──成長産業で、国としても投資領域に挙げているマーケットだからこそ、領域が広がっているのでしょうか?
安藤:拡大するマーケットは、採用や組織を作る戦いも非常に大きいので、我々はいろいろな取り組みができると思います。
この領域の面白さは、変化感や産業の大きさだと思います。エネルギー産業では、創業から3年で100億くらいに成長する企業もあり、それに伴って組織を作るために採用ニーズが非常に高くなります。ここが止まると事業が止まるという緊急性が高いセンターなので、支援できたときは非常にやりがいを感じますね。
Q2. 会社として大切にしている「do/don't」は?
──Leaf Ringさんが力を入れている、「do=やること」をお聞かせください。
安藤:「信頼を積み重ねる」「オーナーシップを持つ」「組織内での貢献」などがありますが、中でも「仕組み化」は非常に大事にしている価値観です。
──HR事業は、ハイプレイヤーにノウハウが属人化されたり、行動量で何とかするという労働集約な側面もあったりと仕組み化は非常に難しそうですが、どのような工夫をされていますか?
安藤:最も重要なのは、情報の貯め方です。例えば求職者と面談したときに、その方の転職理由や希望などを全部一つのカラムでまとめるやり方もありますが、複数のカラムで細かく情報を定義して整理すると、後々、希望条件をセットしたらマッチングできるデータベースとしての使い方ができます。情報の残し方で、その後の情報の使い方が大きく変わってくるのです。
情報をどう取りまとめて、社内でどう使える状態にするのかを重視し、全体で共有することを大事にしてきたので、結果的に仕組み化や効率化につながっていると思います。
──多くのスタートアップが質に投資ができるのはもっと先のフェーズだと思いますが、なぜ創業期から仕組み化に投資すると決められたのですか?
安藤:これは、岡崎の思想がかなり強く出ています。彼は、イエールという事業を立ち上げて相当な量のオペレーションをさばいてきているので、初期における情報設計が甘いと、後でそれをリプレースし見直すときの負債が非常に大きいとわかっています。桜井も、もともと大和証券でデータを整理することに非常に長けているので、その掛け合わせがLeaf Ringの基盤を作っていると思います。
──次に、「やらないこと=don’t」を教えてください。
安藤:「売り上げを重視した意思決定をしない」「非効率な領域に対して量を投下しない」ことにこだわっています。一般的なスタートアップと違い、我々はそもそも上場を目指さない、外部資本を入れないことを根底とし、自分たちが定めたラインまでにいくら伸ばしていくのかという計画をもとに事業をするのが大前提です。
──スタートアップはスピードが勝負だから、やれることを全部やろうという意思決定になりがちだと思うのですが、御社はいかがですか?
安藤:新しい競合他社が生まれることも、量で攻められることももちろんあると思います。しかし、企業様からは「ここまで詳しいコンサルタントは普通じゃない。だからこそLeaf Ringに相談したい」と高く評価していただいているので、他社がどう出てこようとも質で価値提供していきます。
──それが「フォーカスオン」という言葉に込められているのでしょうか。
安藤:そうですね。フォーカスというと「優先順位を決めて、最重要なところに投資せよ」と考えがちですが、やること・やらないことを決めることが重要だと思っています。それで「劣後順位を決定する」というキーワードを入れています。
例えば、企業から求人が来ると、データベースで条件に当てはまる人全員ではなく、本当にマッチしている人にピンポイントで声をかけます。確率を上げるために量をかけるのではなく質にこだわることで、濃密に情報提供ができ、確度が高くなります。その結果、求人が出てから7営業日くらいで売り上げになるようなスピーディーな動きも可能になります。
──すごいですね。求職者の量を確保することに振り切りがちな企業が多い中で、全く違う戦い方をされているのですね。
Q3. Leaf Ringに転職した理由、転職して良かったことは?
──及川さんがLeaf Ringさんに転職されたのはなぜですか?
及川:部門の一員として組織を作っていくというよりは、役員と一緒に組織を作っていけることが大きな理由です。
──日本を代表する企業から、まだ社員数2桁のスタートアップに飛び込むのは、勇気がいることだったのではないでしょうか?
及川:むしろ、会社の一員のままで変化を与えられない方が不安でした。それに加えて、Leaf Ringはビジネスモデル上、何人くらいの採用決定が出れば収益が出るかがわかりやすく、これまでの実績や組織のあり方から、Leaf Ringのやり方で仕事をして売上を出すというモデルを自分も築けると思えたので、安心して入社できました。
──今はどんなお仕事をされているのでしょうか?
及川:コンサル業務、いわゆる候補者さんと企業様のご支援が5割くらいで、それ以外は経営企画、事業企画、デジタルマーケティングなどです。予算を策定し、求人募集の数値を分析しながら、求人の応募最大化を求めていく業務です。
入社当初は社長室というポジションで、プロジェクトを回しながらいろいろなことをやるところに魅力を感じて入社しました。その中で経営企画系や分析系など、自分が得意とする業務に少しずつ重きを寄せていき、人員が足りないので広報とPRも私が担当する感じですね。
──社長室や経営企画は、ともすれば現場がわからないまま数字を叩かなければいけない場面もある中で、主幹事業を半分持っているというのは、解像度が非常に高まりますよね。
及川:入社当初から皆に「自分自身がやらないとだんだん解像度が下がっていくよ」とよく言われていました。「みんな、ここを課題だと感じているんだ」と、日々、解像度を上げつつ、「ここが自動化されたら、みんなうれしいだろう」と自分の実業務としてイメージできるので、やりがいを感じる好循環になっています。
──転職してみてどうでしたか?
及川:キャリア形成という観点で、自分の意思を伝えながら、より自分に適した業務内容に寄せていけているのは、役員陣をはじめ、しっかりサポートできる体制があるからこそだと思っています。
また、個人を尊重し合う文化があり、各々の強みと弱みを把握しながら補完し合うというチーム体制で、ナレッジの共有もできているので、自分らしく働ける環境だと強く感じていますね。
動画にて全編公開中
気になる続きはぜひ動画でご覧ください。
動画内では、5つの質問に加え、企業や事業の魅力解説もご覧いただけます。